前回のブログでは、「シナジーと暖簾(のれん)の相殺」をテーマに、M&A実務の中で本当にシナジーを意識して買収を行っているのか?という疑問で締めくくりました。
今回はその続編として、私のデータベースで整理している実際の事例を一つ取り上げ、M&Aの開示情報において“シナジー”がどのように扱われているかを紹介します。
取り上げるのは、**SchlumbergerによるCameron買収(2016年)**です。
この案件は実施から時間も経過しており、統合後の実績や市場評価を自ら調べることも可能な代表的なケースです。
両社がどのような事業を営んでいたかは、WEBやAIツールを使えばすぐに把握できます。
ここで重要なのは、「自社とは業界が違うから参考にならない」と感じる方こそ、M&Aにおけるシナジー評価の難しさをよく理解されている、という点です。
上場企業の開示資料に記載されるシナジー金額や期待効果は、あくまで投資の正当性をステークホルダーに示すための説明であり、実際のPMI現場で使うKPIや実行基準はそこからは読み取れないのです。
その結果、買収を実務として担う担当者が、PMI段階で「何をKPIに設定し、どう組み立てるべきか」で迷ってしまう構造が生まれます。
Schlumberger × Cameron (2016)
【業界】
Energy / Energy Equipment & Services
【M&A概要】
本件は、エネルギーセクターにおける代表的な統合事例です。
Schlumberger Ltd.は2015年8月、掘削機材メーカーのCameron Internationalを**約127億4,000万ドル(約1.3兆円)**で買収すると発表しました。
Cameron株主は1株あたり現金14.44ドル+Schlumberger株0.716株を受け取り、統合後の会社の約10%を保有。
1株あたり換算では66.36ドルで、当時の終値を約56.3%上回る水準でした。
【想定シナジー】
主なシナジーはコストシナジーであり、特に「調達・生産」の領域で効果が期待されました。
Schlumbergerの発表によると、統合完了後1年目で約3億ドル、2年目で約6億ドルの税引前シナジーを見込んでいました。
主な内訳は以下の通りです:
- 購買・製造の統合によるコスト削減
- 供給網の効率化
- 技術・ブランド資産の共有化
【PMIの焦点】
統合後のPMIでは、組織文化やオペレーションの調整に重点が置かれ、初期段階で明確なガバナンス体制を構築。
シナジー実現のロードマップを策定し、定期的な進捗モニタリングを行ったことが成功要因とされます。
【示唆・学び】
本事例は、M&Aにおける定性的なシナジーを定量的KPIに結び付けることで、統合後の価値創出を可視化できる好例です。
特にPMI初期段階でシナジーKPIを設定し、進捗を定期モニタリングする仕組みが、持続的な企業価値の向上に直結します。
#M&A #シナジー #PMI #企業統合 #経営戦略 #SynergyIndex #事例研究 #シナジー評価 #のれん #M&A分析

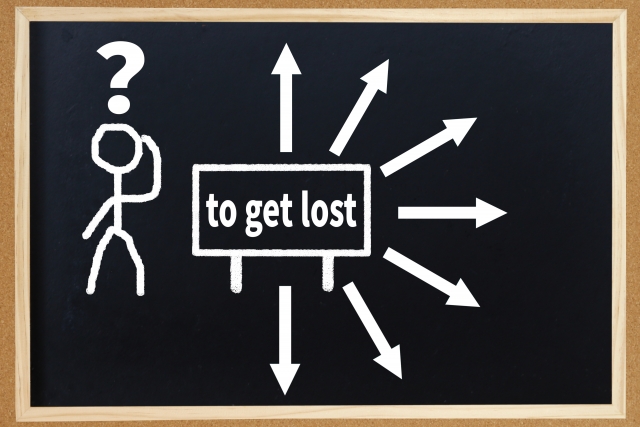


コメント