- はじめに:AIと歩んだ、迷いの道のり
前回のブログで提示した、定年後の6つの選択肢を振り返りつつ、再雇用制度だけではない、自分の未来を深く掘り下げて考え始めました。 当初の6つの選択肢は、それぞれ独立したものではなく、互いに関連し合う複雑なものでした(つまりMECEではない)。しかし、**Geminiとの「壁打ち」**を重ねる中で、一つの答えではなく、複数の要素を組み合わせた「ハイブリッドな生き方」にたどり着くことができたのです。定年前の転職は家族にもなかなか話しにくいものですが、夜な夜なノートPC相手に相談ができるAIは、現代の文明の利器だと改めて感じました。
- 漠然とした問いを、具体的なシミュレーションへ
AIとの対話は、**「仕事の充実感」「経済性」「得意なこと」「趣味」**といった漠然としたテーマを、具体的な検討事項へと落とし込んでいくプロセスでした。AIを使い慣れている方ならご存知の通り、出てきた答えにさらに踏み込んだ質問を繰り返していく作業です。
特に重要だったのが、**「経済性」**というテーマを深く掘り下げたことです。具体的なシミュレーションの例として、「退職後の妻の扶養はどうなるのか」「社会保障費や節税の観点から最も有利な働き方は何か」といった、誰もが気になる現実的な問いをAIに投げかけました。定年後の再雇用の賃金や退職金の受け取り方などをAIに入力すれば、社会保険料や所得税を計算し、瞬時にエクセルに出力してくれるのです。税理士や社労士に頼らずとも答えが出せることに、本当に驚きました。
これらの対話を通じて、私はある具体的な結論にたどり着きました。それは、これまでの健保の継続加入でも、国民健康保険でもなく、協会健保に加入できる合同会社でのマイクロ起業が、経済的な自立への有益な選択肢であるということです。
次回予告:専門知識と趣味を融合させた「二刀流」戦略
いかがでしたでしょうか。AIとの対話は、漠然とした不安を具体的な数字で可視化し、私たちが抱える課題の解決策を、専門家を介さずとも見つけ出せる強力なツールになり得ます。
次回は、私がこの対話から導き出した「ハイブリッドな定年起業」について、さらに詳しくお話しします。
具体的には、
- これまでのM&Aの専門知識を活かしたコンサル業の業務委託
- そして、人生を豊かにする趣味(カフェでの開業など)を活かした事業運営
この2つの「二刀流戦略」が、いかにして生まれ、どのようにして私の定年後の人生を形作っていくのか。複雑な人生の選択肢をAIと整理したプロセスを、皆さんと共有したいと思います。どうぞお楽しみに。
#定年起業 #AIと起業 #セカンドキャリア #マイクロ起業 #ハイブリッドワーク

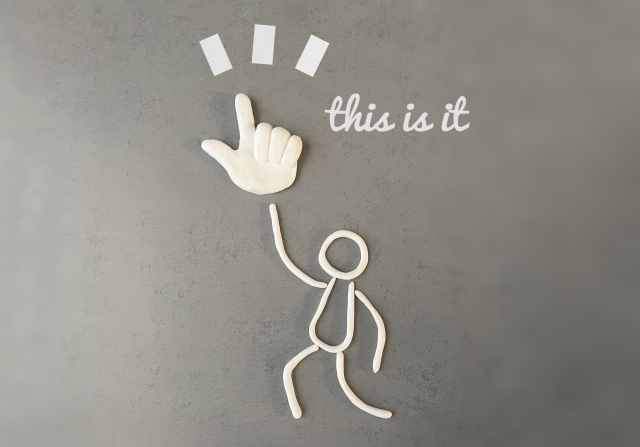
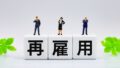

コメント