皆さん、初めまして!
この度、株式会社創夢パートナーズのブログチャンネルを開設いたしました。代表の荒井です。
2025年5月23日に創業し、ようやく皆さまにご挨拶できる運びとなりました。創業までの準備期間から今日に至るまで、様々な出来事がありました。本来であれば、そのあたりの道のりを時系列でお話ししたいところですが、まずは第一回目の投稿として、今最もお伝えしたいことから始めることにしました。
退職後の企業型確定拠出年金をiDeCoに移換しました!
さて、本日の本題です。
私ごとではありますが、先日、退職後の企業型確定拠出年金(DC)をiDeCo(個人型確定拠出年金)に移換する手続きが完了しました!
前職を退職して独立した際、退職金と確定拠出年金に関する案内を受け取りました。正直なところ、様々な「呼称」が飛び交い、何が何だか混乱してしまったんです。特に、「退職金」も「企業型確定拠出年金」も、どちらも「年金」という言葉と強く結びつくため、前職勤務先からの案内書もその視点での説明が中心となっており、余計に頭がこんがらがってしまいました。「老齢年金のシミュレーション」「DC確定年金のiDeCoへの移行」など、似たような言葉が並び、自分のお金がどうなるのか、どうするのがベストなのか、頭を悩ませました。
こういう事、コンサル業開業なのにお恥ずかしいのですが、改めて調べて整理する中で、**「退職金(一時金)」と「企業型確定拠出年金(DC)」**は、全く別のものとして扱うべきだと明確に理解した次第です。
- 会社の退職金制度に基づく「退職一時金」: これは勤続年数に応じて積み立てられた、いわば「給与の後払い」のようなものです。私の場合は、一時金として受け取る選択をしました。一般的に、一時金として受け取ると「退職所得控除」という大きな税制優遇が適用されるため、手取り額が最も多くなる可能性が高いです。これを直接iDeCoに入れることはできませんが、この資金を元手に、今後のiDeCo掛金を捻出することは可能です。
- 「企業型確定拠出年金(DC)」: これは会社が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する年金制度です。前職で積み立てていたこの資産は、退職時に速やかに対応しないと、手数料がかかる「自動移管」という状態になってしまうリスクがあります。
私が今回完了させたのは、後者の「企業型確定拠出年金(DC)」の資産を「iDeCo」へ移換する手続きです。
なぜiDeCoに移換したのか?
企業型DCの資産をiDeCoに移換したのは、主に以下の理由からです。
- 税制優遇の継続: iDeCoは掛金が全額所得控除、運用益非課税、そして受け取り時にも控除が適用される、非常に強力な税制優遇制度です。このメリットを退職後も継続して享受したかったのです。
- 運用商品の選択肢の広さ: 企業型DCでは限られていた運用商品の選択肢が、iDeCoでは格段に広がります。自分のリスク許容度や投資方針に合わせて、より柔軟な運用ができるようになりました。
- 資産のポータビリティ: 独立後も、iDeCoであれば資産を自分自身で管理し続けることができます。
手続きは驚くほど簡単でした(実体験)
正直なところ、手続きは少し複雑なのではないかと構えていましたが、いざ始めてみると、驚くほどスムーズに進めることができました。
私の場合、すでにSBI証券で投資口座を開設済みだったため、その既存口座を利用してiDeCoの移換手続きを進められたのが非常に大きかったです。新たに口座を開設する手間がなく、申請処理は全てオンラインで完結しました。書類の郵送なども不要で、システムの手順に沿って進めるだけで、10分もかからずに必要事項の入力が完了したほどです。
この作業を週末に実施したため、現時点では週明けの審査完了を待っているところです。無事に完了の連絡が来れば、安心して運用をスタートできます。
今回の経験を通じて、改めて資産形成における情報収集と早期の行動、そして適切なプラットフォーム選びの重要性を痛感しました。特に、独立して会社経営を始める中で、自分自身の老後資金についても計画的に準備していくことの必要性を強く感じています。
これから皆さまにお届けしたいこと
株式会社創夢パートナーズでは、定年前後で会社をリタイアされ、セカンドライフを迎えようとしている皆さまが、安心して新たな人生をスタートできるよう、様々な情報やサービスを提供してまいります。
今回のiDeCoの話題のように、一見すると難しく感じる資産形成や年金に関する知識も、皆さまのセカンドライフを豊かにするための重要な要素です。私自身の退職や独立の経験も踏まえ、複雑になりがちな退職後の手続きやお金の管理について、実体験を交えながら分かりやすくお伝えしていければと考えています。
このブログでは、私がこれまでの経験で培ってきた知識や、日々の業務で得た学びを、分かりやすく、そして皆さまのお役に立てる形で発信していきたいと思っています。
次回以降は、具体的にどのようなテーマについてお話ししていくか、近いうちにご紹介できればと考えておりますので、どうぞご期待ください!
最後に
初回から長文になってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。
創夢パートナーズは、皆さまのビジネスの成長をサポートできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

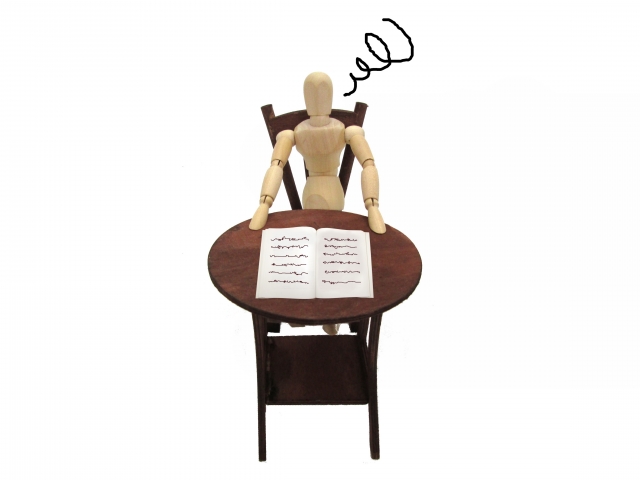

コメント